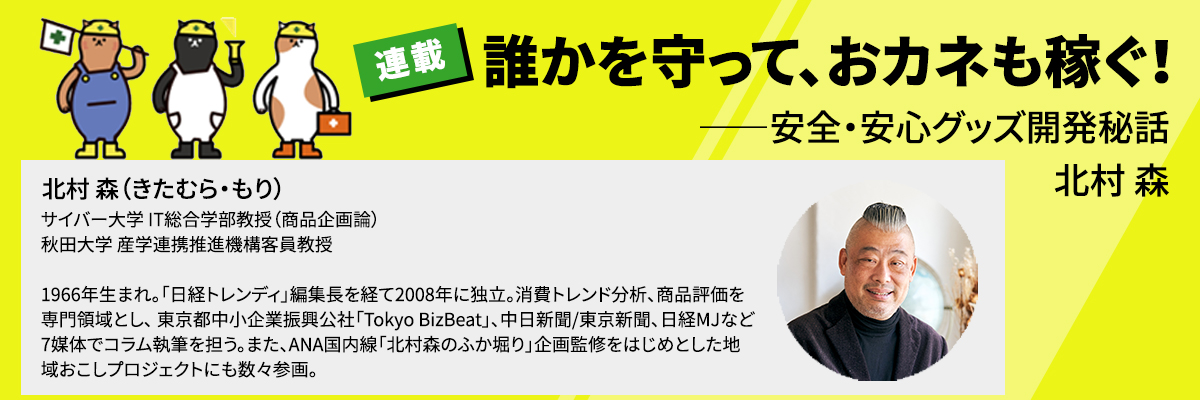
連載❹「業界初」に挑んだ、人々に切実な理由(タンゲ化学工業株式会社)
【DATA】製造元:タンゲ化学工業株式会社(愛知県 名古屋市)
商品説明:状況に応じて灯油、軽油、水、湯と、入れるものを選んで使えるタンク
商品仕様:サイズ/幅35×高さ34×奥行き24.5㎝ 容量/20ℓ 素材/ポリエチレン
詳細:https://www.tange-kagaku.co.jp/newitem/bousaikan.html

上の画像が今回取り上げる商品です。容量が20ℓのポリタンクで、その名を「防災缶」といいます。ポリエチレン製の商品ですが、業界の慣行上、「缶」と名づけていると聞きました。価格は3,300円(税込)です。
どうということのないポリタンクに見えますね。でも、今年(2025年)に発売となったこの「防災缶」は、業界初という商品なのだといいます。どういうことか。
灯油、軽油、水、湯。このポリタンクを購入したユーザーは、最初にこれら4つのうち、何を入れるかを任意に決めて、それ専用のタンクとして使うことができます(途中で別の液体に入れ替えることはできません。最初に決めた液体を入れ続けることになる)。このような使い方ができる点が、業界初だという話です。
この「防災缶」を開発し、製造・販売しているのは、愛知県名古屋市に本社のあるタンゲ化学工業です。1932年創業という企業で、プラスチック家庭用品の製造に長年携わっています。ほぼすべての商品が自社ブランドで、国内での生産であるそうです。同社によると、湯たんぽの国内シェアは約3割といいますから、小さくても実力のある企業と表現して差し支えないでしょう。
そんな同社は、かねてからポリタンクも製造していたと聞きますが、4つの液体に対応する商品を完成させるのは初めてのことでした。業界初というのですから、まあそうですね
いざというときに商品がない
ここで皆さん、「どうして4つの液体に対応するポリタンクが必要なのか」、また「なぜそうした商品がこれまでなかったのか」と感じられるかもしれません。私自身もそうでした。同社を訪れて、どういうことなのかと、社長にじっくりと聞いてきました。
まず、前提として、既存のポリタンクというのは、灯油用、軽油用、水用といったように、入れる液体によって商品が厳格に区別され、販売されてきたといいます。その理由は「灯油や軽油ならば消防法、水ならば食品衛生法と、適合させるべき法律が異なる」からと社長に教わりました。本体の加工の仕方なども当然異なってきます。だから、ホームセンターに行くと、それぞれの液体向けに分けたポリタンクがあるわけですね。そしてユーザーが間違わないように、各メーカーは本体の色も変えているらしい。
ユーザーにすれば、どのみち、最初に入れた液体から途中で違う液体に変えて使うことはできませんね(灯油を入れていたポリタンクに、途中から飲料用の水を入れるなどあり得ないので)。なのに、またなぜタンゲ化学工業は、業界にそれまで存在していなかった「防災缶」を開発しようと決めたのか。
「自然災害が起きたときに、使い手にとって切実に必要なポリタンクが品切れで行き渡らないという大問題があるからです」。そう社長は話します。
東日本大震災に見舞われたのは2011年3月のことでした。春を迎えつつあるこの時期、「私たちを含めた各メーカーは、冬場に動く灯油用ポリタンクの製造はすでに終えていて、春夏向けの水タンクにシフトしていた」そうです。東北の被災地はまだまだ寒く、灯油を入れるタンクの要請が相次いでいたのに、メーカーは対応しきれませんでした。急きょ増産したくても、金型を配備し直して、素材の色を変える体制をすぐに整えるのは、きわめて困難でした。
その後も、各地で震災が発生するたびに、社長は心を痛めたといいます。「災害は時期を問わない」と身にしみて感じたと振り返ります。

すべてに対応できるポリタンクを
ならば、どうする? 社長は思い立ちます。「灯油用、軽油用、水用と別物だったポリタンクを統一する商品をつくればいい」
先ほど触れましたように、手にしたユーザーが最初に何を入れるのかを好きに決めて、灯油用としたり、軽油用としたり、水用としたりできるポリタンクが商品として存在すれば助かるはずだ。どんな時期に災害に見舞われても、特定の液体向けのポリタンクが市場で払底していても、困っている人がちゃんと使えるように、という話です。
私はここまでの経緯を聞いて、とても納得できました。商品開発に必要なのは違和感や疑問を見逃さない姿勢です。タンゲ化学工業の社長は、業界で当たり前であった「液体によって別物のポリタンク」という部分こそが問題であると斬り込んだ。まず、そこを評価したい。
ただ、実際に開発するとなると、いろいろな困難がありました。本体の素材をどうするかの検討ひとつそうです。社長によると「軽油が最も厳しい適合基準」であるそうで、そのレベルに合わせた素地と加工法を用いることに決めました。ただし、飲料とすることが前提の水でも使えるようにとなると、そこでも素材の吟味は必要でした。
次に手間がかかるのは、それぞれの法律への適合です。灯油、軽油、そして水といったふうに、すべてをクリアしないといけません。社長はそれを躊躇なく進めていったそうです。その結果、上の画像にあるように、本体には消防法と食品衛生法という2つの適合シールが貼付されています。

小売店が、その意義を理解し始めた
こうして2025年、業界初となる「防災缶」は完成します。社長に「開発するうえで何がいちばん大変だったか」と尋ねたら、意外な答えが返ってきました。私はてっきり、素材や加工法を見いだす経緯や、それぞれの液体に適合させる手続きにあったのかと思っていたら、そうではなかった。
「本体の表面に貼ったラベルのデザインです」と社長はいいます。
確かにこの「防災缶」は、切迫した個別の状況に応じて灯油でも軽油でも水でも湯でも入れられるポリタンクですが、先ほどお伝えしたように、ユーザーは最初に何を入れるかを決めて、その後は灯油なら灯油、軽油なら軽油で使う必要があります。「そこをいかに間違えずに使ってもらえるか、この商品の特性をどうやってひと目で理解してもらえるか、そこが絶対に大事になる」。だから社長は、本体のラベルのデザインワークこそが問われると判断した。
「試作は50パターン以上に及びました」と社長はいいます。その結果、上の画像にあるように、わかりやすいデザイン(かつ、ユーザーが最初に、入れる液体に印を付ける形)に決めたそうです。
業界にとっても、多くの消費者にとっても、きわめて画期的な商品の登場に思えます。それでも…。
「主力の販売先となるホームセンター業界からの反応は、当初低調だった」と社長はいいます。商品説明を試みても「うちの店舗には、それぞれの液体のためのポリタンクをちゃんと取り揃えて売っているから」とあしらわれることが多々あったそうです。
「いや、そうじゃない。この商品は平常時のための存在ではない。いざというときのための存在なんだ」と、社長は粘り強く、流通小売各社に伝え続けます。大きな展示会にも「防災缶」を携えてブース出展しました。
その結果…。「ようやく、『なるほど』と理解し、振り向いてくれるホームセンターが現れ始めた」そうです。「普段はさほど売れないとしても、この商品を店舗に並べておくことこそがホームセンターの責務だと言ってくれるところが複数出てきました」。
社長の思いを受け止めるホームセンターが登場してきたのは、とても大きな話だと感じます。
「私の会社は、必ずしも万人向けの商品づくりを目指してはいません」と社長は力説します。「よそが苦手とするところで戦う、それもまたひとつの勝ち方なのだと考えています」。
そうした方針であるから、「防災缶」は完成し、いざというときのために、これからも市場に存在し続けるのだと思います。




